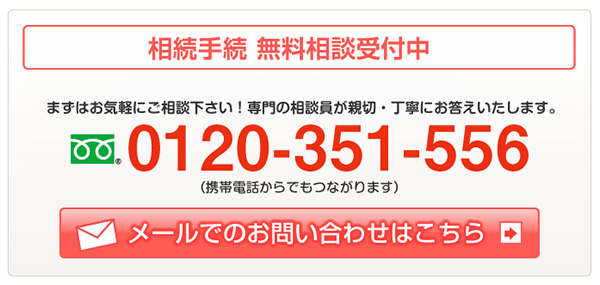【相続コラム】相続人が海外在住だったらどうなるの?

海外で暮らす日本人の数は増加傾向にあります。2020年10月1日の統計によると、135万7,724人の方が海外に在留しています。
さて、もしも相続人が海外在住だった場合の相続手続きは一体どうなるのでしょうか?
相続手続きには三種の神器と呼ばれるものがあります。それが、
1. 今回亡くなられた方の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 相続人全員の印鑑証明書
の3つです。
相続手続きとは、この三種の神器を揃えて、
① 「手続き先の所定の用紙」か「遺産分割協議書」に実印を押して提出する
② 亡くなられた方の名義になっているものを、解約するか、名義変更する
が基本的な流れになります。(三種の神器は1つでも欠けていれば、②は進みません)
話を戻しますが、相続人が海外在住だった場合は何が問題となるでしょうか。
それは、「印鑑証明書が取得できない」ことです。
印鑑証明書とは、日本の住所地で登録するもの。つまり海外に在住して日本に住所が無いのなら、「印鑑証明書を発行してもらえない」んですね。
印鑑証明書がないということは、「所定の用紙」か「協議書」に捺印しても、それが本人のものであるという証明ができません。
いつまでたっても解約や名義変更ができない・・という話になってしまいます。
これを解決するのが「サイン証明」です。
サイン証明とは、現地の日本大使館もしくは領事館で作成してもらう証明書のこと。相続人本人が大使館か領事館に出向き、職員の前で遺産分割協議書に実印ではなくサインし、「このサインは〇〇さんのもので間違いありません」と記載、印鑑証明書に代わる証明書です。
ちなみにこのサイン証明という制度、もしも日本に一時帰国できるなら、日本の公証役場でも手続きが可能です。
また、手続きによっては「相続人の住民票」が必要な場合もあります。その場合も同じく、住民票の代わりに現地の領事館で「在留証明書」を取得する必要が出てきます。
このように、相続人が一人でも海外に在住している場合は、どうしても手続きが煩雑になってしまうのです。
事前に遺産分割協議書を作成し海外に郵送する、サイン証明を日本に郵送するなど、やり取りで時間も多くかかってしまいます。
しかし、海外に相続人が在住していても、問題なく手続きを進める場合があります。
それが、遺言書がある場合です。
遺言書の一番の特徴は、遺言書通りに遺産分割が可能なこと。遺言書があれば、実印を押した「所定の用紙」や「協議書」も、印鑑証明書も必要ありません。
海外在住の相続人がいるケースの手続きがあると、「もし遺言書があれば、どれだけ早く相続手続きが終わることか・・」といつも考えてしまいます。
というわけで、今回のまとめです。
・現地の領事館か大使館でサイン証明を取得する
・一時帰国できるなら、公証役場でサイン証明を取得する
・自分の相続人が海外に住んでいるのなら、遺言書を作成しておく
お困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。